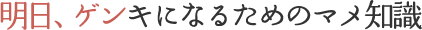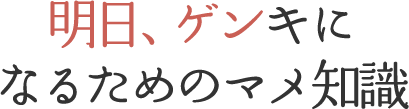SDGs「電気自動車(EV)に乗って考えたこと」SDGs目標 No.13 気候変動に具体的な対策を
私は5年ほど前から動力が100%電気の電気自動車(以下、Electric Vehicle:EV)に乗っています。EVと言えば、排気ガスを出さないクリーンな乗り物として世界の注目を集めています。さて、コロナ禍において、2020年4月から2023年2月までの3年弱、私は職場まで、それまでの電車通勤に代えて車で通勤していました。ある日、対向車線を走る車のうち何台がEVなのか数えてみることにしました。結果は100台中0台! さらに100台数えたところ、やっと1台を見つけることができました。このことからEVの割合は、おそらく走っている車の1%未満だろうと推測できたものの、二酸化炭素削減の一手として政府が普及を目指しているEVとしては、ちょっと寂しい結果となりました。実際2022年の各国におけるEV普及率を調べてみたところ、以下の状況であることが分かりました。あながち私の概算も捨てたものではないようです(笑)。
(参考)https://ev-charge.enechange.jp/articles/033/
近年、地球温暖化が深刻になっており、世界全体で2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す動きが広がっています。温暖化の原因である二酸化炭素排出量削減のための強力な一手として注目を集めている手段がガソリン車からEVへの移行です。
日本をはじめとした先進国を含め、世界各国でEV完全普及を目指しており、2030年度から2040年度までにガソリン車とディーゼル車に新車販売を禁止するとした政策が打ち出されています。
今回の記事を書くにあたって、知りたいことがありました。
「北欧は日本より寒いのに、なぜ日本よりEV普及率が高いのか?」
ご存じのように寒い気候では充電池への負担が大きくなることが良く知られています。
<結 論>
1)国家が近接しているヨーロッパにおいて他国の環境汚染は他国だけでは収まらないものと考える人が多く、かつ自然が豊かなことから自国、他国を問わず環境保全への意識が高い。
2)ノルウェーをはじめ北欧はあまりにも寒いため((例)ノルウェーの首都オスロの冬期:平均-6℃、最低-30℃(概値))、エンジンオイル(*1)が固まらないように普通のエンジン車には " ブロックヒーター " というヒーターが附属しており、その電源コンセントが車庫には付いている。したがって各家庭の駐車場、公共駐車場には必ず電源(230V)があり、冬期に車にコンセントをつなぐ行為に抵抗がない。
3)2)を行うための電気インフラがすでに整っており、公共の充電設備を新たに設置する場合、その障壁が低い。
4)EV購入・利用にあたって政府からの補助金が厚い。
5)会社の車を貸与されている人が多く、それがEVである。
蛇足ですが、2030年代にはヨーロッパでは、主要都市にガソリン車、ディーゼル車は入ることができなくなるとの話をも聞こえてきます。これもEVへの移行が加速している原因かもしれません。
(*1:日本国内で入手可能なエンジンオイル「0 Winter」(Winterは"冬"を表し、オイルが外気温何度まで使用出来るかの基準)であれば-35℃まで使用可能、北海道では「5 Winter」(-30℃まで使用可能)で十分とされる))
さて、今後EV購入を検討されている方の参考になるかもしれないと考え、私がEVに乗ってみて感じたその長所と短所を羅列してみたいと思います。
<長 所>
1:エンジン音が無く「ヒュイーン」というモーター音しか聞こえず、とても静か。加速する時もモーターが頑張っている感じが無い為、道路を滑るように走る(知り合いはこの加速に対して「宇宙船みたいだ!」ととても喜んでいた)。
2:100%電気のEVに乗っていることで地球環境を良くすることに貢献している気がする。
3:航続距離が長くないため(私の場合100%充電で200km弱)、遠くに出かけるときは充電設備のある場所(ディーラー、コンビニ、コミュニティーセンターなど)をあらかじめ調べておく必要があるため旅程が計画的になる。この際思わぬ観光スポットを見つけたり、充電中に地元の方と交流できたりするため楽しい。
4:ガソリン車に比べ、充電のため強制的に休憩を取らされるが、このお陰で長距離ドライブにおける疲労が溜まりにくく快適。
<短 所>
1:充電に時間がかかる(急速充電の場合であってもゼロから満タンまで1時間かかる。ちなみにガソリン車は長くても2分)
2:急いで遠くに行かないといけない時、充電量が足りていないと充電のため、出発が遅れる。
3:たまに充電スタンドに先客がいて、長いと数十分待たないといけない(充電渋滞。休暇時の高速道路サービスエリアなど)。
4:航続距離がガソリン車に比べ短目。
5:車両の値段がガソリン車に比べ高価。
6:暖房は充電池の電力を使うため、雪道渋滞の可能性があるときには絶対に乗れない。
7:燃料(電力)切れの時、ガソリン車と異なり燃料である電気を運んでくるわけにはいかないためJAFを呼ばないといけない可能性がある。
短所についてはEV普及率の高いノルウェーでも同様のことが起きているようです。これらの点をどう改善していくのかを、今後日本はノルウェーをはじめとする北欧諸国から学ぶ必要があるでしょう。
とはいえ、2023年3月現在、自動車メーカーは航続距離が500kmを超えるような車種を市場に送り出してきています。今後の技術革新により、充電時間はより短くなり、航続距離はより長くなり、そして車体価格もガソリン車並みに安くなれば、日本でもEVの普及がもっと進むのではないでしょうか。もちろん燃料となる電気の発電・送電方法についても進歩が見られるでしょう。カーシェアリングなどの体制も組み合わせることでよりEVが私たちにとっての身近なものになり、その活躍の場が広がっていくかもしれません。その時には私たちの環境への考え方も大きく変わっていて、「これからの地球環境を考えるなら、第一選択はEV」となるのかもしれません。
(参考)「複数の交通政策を考慮したEVライフサイクルアセスメントに関する研究」交易財団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.57 No.3, 2022年 10月
月別アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年