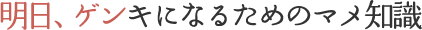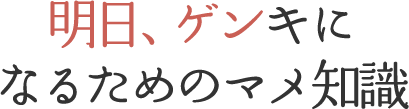ハンガーノック
季節は春になり、菜の花や桜の花が咲いています。暖かくなってくるとどこかに出かけたくなりませんか。
近くの公園でもいいし、少し足を延ばして郊外の野山をハイキングするのもいいでしょう。
その時はお昼に食べるお弁当と飲み物も忘れないでください。
でも現地で食べる予定だったお弁当や飲み物を忘れてしまったら? 周りに買うお店が無かったら?
あなたは空腹を抱えて出発地点まで戻らなくてはいけないかもしれません。
もし空腹状態が長い間続くと、あなたは動けなくなってしまうでしょう。
この状態のことを「ハンガーノック」(体の燃料切れ)と言います。
ハンガーノックは長時間の激しい運動(フルマラソン、自転車競技など)によって
引き起こされた低血糖状態を指します。
マラソンのテレビ中継で残り数キロで選手が失速するシーンを見られたことがあるかもしれません。
一方でこうならないために選手がスポーツドリンクなどの補給を受け取るシーンを
ご覧になったことがあるかと思います。
あれは運動によってどんどん消費される糖を一定レベルに保つための行動です。
なおハンガーノックは日常生活で経験することは稀と言われます。
ハンガーノックの具体的な症状としては、めまい、判断力の低下、
自分の意志とは関係なく運動のできなくなる、強い疲労感・倦怠感があります。
この状態からの回復方法としては、急いでアメやお菓子などの
高炭水化物食を水分と一緒に摂ることにより回復します。
ただこの症状に陥ってしまった場合、簡単には元の状態に回復することはできません。
私の経験上、どんなに早くても15分、通常は30分ほどかかるため、
競技であれば順位を落とすことを確実です。したがってこれを防ぐための方法がいくつかあります。
1)カーボローディング
体に炭水化物をため込む目的で食事を摂ることです。
長時間の運動を継続するために必要なグリコーゲン(食事に由来する炭水化物に由来)を
その貯蔵先である肝臓と筋肉に貯めるため、通常より炭水化物を多めに摂取することです。
具体的な方法は他に譲りますが、簡単なところでは、競技前日の夕食のご飯を1杯多く摂るとか、
当日朝の食事はお餅を3~4個摂るなどがあります。
2)活動中のこまめな補給
こちらの方がカーボローディングより大事なのではないかと思います。
活動の休憩時間に食物を摂取することはもちろん、可能であれば、15~30分毎にアラームが鳴るように
タイマーをセットし、鳴るごとに食べ物を摂るようにします。
アラームをセットするのは活動に集中し、食べ物を補給することをうっかり忘れてしまうことを防ぐためです。
このようにして空腹を感じていなくても何か食べ物を摂取するように心がけます。
体の燃料を最後まで使い切ってしまう前に足していくという感じでしょうか。
一旦体内の燃料タンクがゼロになってしまった場合、人間の身体は自動車にガソリンを補給する場合と異なり、
食べてもそれらはまず最初に、体が燃料を利用するエンジンを動かすために使われ、
すぐには燃料を体に回すことができませんし、
一度にたくさん食事を摂ると消化のために内臓に血流を持って行かれてしまい、
体に燃料を回すのが遅れ回復が遅れるでしょう。
以上のことから、活動を止めず、消化器官にも負担をかけることなく、
体内のエネルギーレベルを保つためにも「こまめな補給」が大切なのです。
3)活動の強度を上げ過ぎない
炭水化物は高強度の運動を可能にしますが、
それによる持続時間は長くはありません。したがってなるべく高い強度の運動にならないように、
自身の身体能力を把握し燃料の無駄遣いをしない、つまり適切な活動強度を保つことにより炭水化物ではなく、
脂肪を主な燃料として使用することを心掛ける、という方法もあります。
炭水化物は3大栄養素の中で最もエネルギーへの変換効率が高いため、体内では真っ先に使われます。
それを使い果たすと、体は筋肉を分解してエネルギーを生み出します。
それもなくなった時が脂肪の出番となります。
人は進化の過程で、生き残るため一番エネルギー産生が高いものの、
エネルギーへの変換効率が悪い脂肪を一番最後に使うように進化してきました。
ですから極論を言えばハンガーノックになったからと言って、
体の中のエネルギー源をすべて使い切ったわけではないのです。
とは言え、何でも早め早めの対応が大切ですね。
月別アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年